| お知らせ |
 10/30(土)18:30-20:30、5月より延期となっていた米谷匡史(思想史)「大阪朝鮮詩人集団のサークル文化運動 ――詩誌『ヂンダレ』と「流民の記憶」」を開講します。 10/30(土)18:30-20:30、5月より延期となっていた米谷匡史(思想史)「大阪朝鮮詩人集団のサークル文化運動 ――詩誌『ヂンダレ』と「流民の記憶」」を開講します。
- <2010/10/26>第3期の記録をアップしました。
|
|
 |
 |

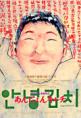 
|
 |
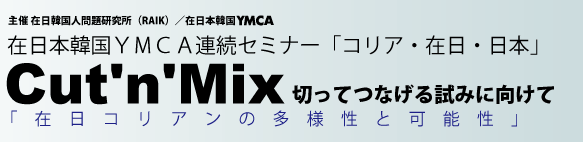
Cut
and Mix通信 第14号
「コリア・在日・日本」連続セミナー2002〜2003
第13回 皮 進さん
「民族教育の新しい試み」 多様化の中の民族教育
|

|
 |
|
|
●李 相 勲(牧師)
朴訥な感じをどことなく漂わした皮進さんのお話は、たいへん興味深いものでした。とくに鶴見の民族学校建設にまつわる逸話などからは、民族学校に携わった人たちの汗の匂いとともに、当時の人たちの民族学校や自分の子どもの将来に対してもっていたであろう熱い思いと期待が伝わってくるようでした。また、民族学校の歴史を学ぶ中で、1948年当時に起こった一連の民族学校への弾圧事件(阪神教育闘争など)が、「国立大学受験資格」や「税制優遇措置」をインターナショナル・スクールには与えるが、朝鮮学校をはじめとする民族学校には与えないとした、現在の文部科学省の不当な民族差別的な決定に象徴的に現れているように、現在も続いていることなのだということも実感することができました。
しかし、皮進さんの講演の中で、最も面白いと思ったのは、朝鮮学校が今、変わりつつあるという事実でした。しかも、父母たちの、時代に即した教育をして欲しいとの要請によって。日本の中には、朝鮮学校に対する偏見が多々あると思いますが、このような事実を聴くことを通して、そのような偏見が少しでもなくなるよう祈るばかりです。
皮進さんは、講演の中で、何度か民族教育の課題は、「民族の一員としてのアイデンティティの確立」であるとおっしゃっていました。僕もそれに同感です。僕も自分の現場(在日大韓基督教会の子どもたち相手の日曜学校)でそのことを考えながらも、日々刻々と広がっていく在日の「多様化」に圧倒されています。そのような現実の中で、「民族の一員としてのアイデンティティの確立」といった時の「民族」の概念が様々な所で問われてきているのだと思います。そのことを含めて民族教育について考えるときには、在日コリアンが力を合わせて考える必要を痛感します。その材料の一つとなる民族教育史に関しても同様なことがいえるでしょう。
皮さんは、最初の就学前教育機関として、1953年に始まった鶴見朝鮮幼稚園を挙げておられましたが、実はそれ以前にも「朝鮮幼稚園」は存在しました。僕の知る限りでは、1928年6月に開園した大阪の今宮朝鮮幼稚園がその最初です。この幼稚園は、今宮朝鮮基督教会の付属の幼稚園で、カナダのキリスト教会からの支援で運営されていました。民族教育史を考えるとき、このようなお互いが知っている歴史事実の情報の交換が必要でしょう。その中で、より包括的な歴史を構成し、民族教育への新たな方向性を見ることができたらと思います。
そうそう、皮進さんは、二次会、三次会……でも、素敵な方でしたということを報告して終りたいと思います。
●発行●2003年5月30日
●編集●金 弘 明/洪 貴 義/佐藤信行
|
 |
 |
|
